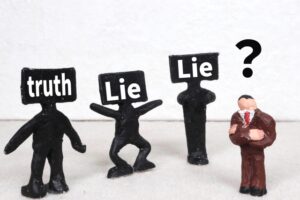組織では「ルール」を定めておく必要があります。
人はルールがないと個人の判断で自由に行動し始めます。
そのため、ある程度のルールがないと、常にバラバラの状態になってしまうからです。
ルールはただ定めればよいわけではなく、ルールの決め方や守らせ方、ルール違反をしたときの処罰の仕方にも工夫が必要です。
今回は、「ルール」の決め方・守らせ方・処罰の仕方についてまとめていきます。
現代社会ではかつてないほど複雑になり、心と体のバランスを崩したりストレスを抱える人が増えています。
また同時に、医療の現場では病気の根底にある心の問題や生活環境など、 その人を包括的にケアできる医療の必要性が叫ばれるようになりました。
そこで注目されているのが「アドラー心理学」です。
アドラー心理学とはオーストリア出身の精神科医・アルフレッド・アドラーによって提唱された心理学の体系です。
アドラーは「人間の悩みはすべて対人関係である」としており、 この講座ではその悩みの根源を知り、幸せへの一歩を踏み出す方法が学べます。
- 自分が変わることで対人関係を好転させる方法
- 自らはもちろん周りの人も勇気づけられる物事の捉え方や考え方
- 他者の行動の受け止め方や言葉がけの方法
- 怒りやイライラと上手く付き合うコツ
非言語コミュニケーションとして子どもから高齢者まで幅広い世代に活用できるアドラー心理学を学び、いろいろな場面で役立てていきましょう。
⇩⇩⇩気になる方はクリック⇩⇩⇩
ルールとはなにか?
「ルール」とはなにか?
それは ”やるべきこと” と ”やってはいけないこと” を明確にしたものです。
そして、その形式には「見える形のもの」と「慣習的なもの」の2つのものがあります。
たとえば、禁煙・右側通行・駐車禁止などのように文字化され掲示されているものは ”見える形のルール” になります。
それとは異なり「挨拶は元気に笑顔でする・整理整頓を行う」など文字にされなくても”慣習的に行っているルール” もあります。
| 禁煙 | 右側通行 | 駐車禁止 | |
|---|---|---|---|
| 見える形のもの |  |  |  |
| 挨拶は元気に笑顔でする | 整理整頓を行う | |
|---|---|---|
| 慣習的なもの |  |  |
ルールの決め方
ルールの作成は、リーダーが独断で行うのではなく、部下の意見を取り入れつつ行うことが理想です。
部下の意見を取り入れることで、現場の意見を取り入れた良いルール作りができるからです。
また、決めるルールの内容は守れないような高い基準のものではなく、あくまで守れる基準のものでなければいけません。
守ることの難しいルールを作ってもいずれ誰も守ることはなくなります。
ルールは「理解しやすく・守りやすく・多すぎず」が重要
ルールを決めるときには、まずそのルールを全職員が理解できることが必須になります。
ルールを理解できなければ守ることもありません。
次に、ルールは理解できても守ることが困難なものではどうしようもありません。
この”守ることができる”というのは、全職員が守ることができるという意味です。
また、ルールはたくさん作れば良いというものではありません。
ルールが多ければ規律を保つことはできますが、まずルールを覚えることが大変です。
これでは、仕事よりもルールばかりを気にしてしまい、逆に業務効率が下がってしまいます。
複数の部署がある場合の注意点
会社内に複数の部署がある場合には、それぞれの部署でルールの基準が大きく異なってしまう場合があります。
このような場合、ルールの厳しさに偏りがないように、リーダーごとで調整する必要があります。
例.2つの部署での「禁煙」のルール
AとBの2つの部署で「喫煙」についてのルールを定めるとし、それぞれ下のようにルールが決定したとします。
- 部署A ⇒ 休憩時間であれば喫煙所での喫煙を認める
- 部署B ⇒ 業務開始から業務終了まで喫煙を認めない
この2つのルールでは、同じ会社内の2つの部署で「禁煙」について異なるルールができてしまいました。
これだと、部署B内の喫煙者は納得がいかず不満の声があがることになります。
ルールの守らせ方
ルールを守らせることはその集団のリーダーの責任ですが、ただ厳しくするだけではルールを守らせることは難しいです。
ルールを守らせるためには、以下の4つの点に注意をする必要があります。
① ルールの必要性を理解してもらう
ルールを決定した理由や根拠を理解できていないと、守らされている方は ”やらされている感覚” しか生まれません。
ルールには守る理由や必要な根拠があります。
理由や根拠がわからずに”ただやらされている”と感じている状態では、似たような事例が起きた場合に対応ができない状態に陥ってしまいます。
まずは、なぜそのルールがあるのかをしっかり理解してもらうことが大切です。
② ルールを自律的に行えるようにする
ルールは部下自身が自律的に行えるようにしなければなりません。
”言われて守る”ではいけない ということです。
リーダーに言われないとルールを守れない部下は、リーダーがその場からいなくなればルールに対して手抜きをします。
自主的にルールを守るために、部下にそのルールの必要性を納得してもらう必要があります。
③ 適度に注意をうながす
ルールは掲示するだけでは意識づけができません。
そのため ”朝礼で読み上げるなど適度に注意をうながす” ことも必要になります。
常日頃からの意識づけを行うことが大切になります。
④ 必要に応じてルールの更新を行う
ルールは守らなければなりませんが絶対ではありません。
”守れないほどの厳しいルールは作ってはいけない” ということです。
ただ、厳しいだけのルールを部下に強いてしまうことは、部下の業務を窮屈にすることになり、自由度がない分、部下はやる気をなくしてしまいます。
そのため、ルールは定期的に見直しを行い、厳しいだけのルールは取り除いていく必要があります。
ルール違反に対しての処罰
ルールを作れば違反者が出ることもあります。
そのようなときにはどうしたらよいのでしょうか?
- 違反者をみんなの前で激しく罰する
- まずはなぜ違反したかを確認する
上の2つを比べるともちろん ”②” が正しいです。
「罪を憎んで人を憎まず」ではないですが、リーダーだからといって何もかもただ怒ればいいというわけではないです。
人を罰する前に、なぜそのようになったかを考えなければなりません。
失敗した人を怒るだけでは、なぜそのことが起こったのかを把握できないですし、改善することもできません。
ルール違反の処罰の仕方については、以下のようなことに注意をする必要があります。
① 事実関係を調べる
ルール違反があったからといって、ただ処罰するだけではいけません。
なぜ、そのようなことになったのかをきちんと確認しなければなりません。
また、それと同時に、本当にその部下が違反したのかも確認しなければなりません。
一方的に処罰してあとで冤罪でした、なんてことを起こしてしまえば、それこそリーダーが処罰対象になります。
② 部下の言い分も聞く
ルール違反があったときには部下の意見も聞かなければなりません。
どのような形であれ、部下にも言い分があるからです。
そこを聞かずに頭ごなしに怒鳴りつけるリーダーもいますが、これからの時代には合わないリーダーです。
部下の言い分を聞き、状況を把握し、事実関係を調べ、その中で部下のできていなかった部分を指摘することが大切です。
③ 今後を部下と共に考える
ルール違反の事実関係を調べ、部下の意見を聞き、部下のできていなかった部分を指摘します。
その上で、これから部下がどのようにしていけばいいかを一緒に考える必要があります。
ここで大切なのは「こうしなさい」と指示を与えるだけにならないことです。
失敗をし、指摘を受け、そこからどうしたらいいかを考えるのは、部下でなくてはなりません。
部下が考え、その考えをサポートすることがリーダーの役目になります。
考えて答えを出すことで、部下は同じ失敗をしなくなります。
④ 改善されているかを確認する
今後どのように改善したらよいかが決まったあとは、それで終わってはいけません。
一定の期間をおいて、改善されているか不具合など生じていないかを確認します。
行動を改善した部下からも異なる視点で何か意見が出るかもしれません。
その中で部下の行動の改善点を探し、ルールに改定が必要ならルールの改定を行う必要があります。
ルールの決め方・守らせ方・処罰のしかた|まとめ
会社や集団にはルールが必要ですが、リーダーが一方的に厳しいルールを作り、無理矢理守らせ、厳しく処罰するという形ではもはや独裁者と変わりません。
ルールはリーダー個人のために作るものではなく、その集団に所属する人すべてのために作るものです。
必要性があるものをきちんと守れるようにルールを作りみんなで守っていきましょう。
現代社会ではかつてないほど複雑になり、心と体のバランスを崩したりストレスを抱える人が増えています。
また同時に、医療の現場では病気の根底にある心の問題や生活環境など、 その人を包括的にケアできる医療の必要性が叫ばれるようになりました。
そこで注目されているのが「アドラー心理学」です。
アドラー心理学とはオーストリア出身の精神科医・アルフレッド・アドラーによって提唱された心理学の体系です。
アドラーは「人間の悩みはすべて対人関係である」としており、 この講座ではその悩みの根源を知り、幸せへの一歩を踏み出す方法が学べます。
- 自分が変わることで対人関係を好転させる方法
- 自らはもちろん周りの人も勇気づけられる物事の捉え方や考え方
- 他者の行動の受け止め方や言葉がけの方法
- 怒りやイライラと上手く付き合うコツ
非言語コミュニケーションとして子どもから高齢者まで幅広い世代に活用できるアドラー心理学を学び、いろいろな場面で役立てていきましょう。
⇩⇩⇩気になる方はクリック⇩⇩⇩